
第1章 序 論
1.1 研究の背景
コミュニケーションとは、「ことば」の音声表現、顔の表情、身振り手振りなどで相手に意思や考えを伝えるやりとりをいう。人のコミュニケーションは知識や意思の伝達による、相互理解を目的としている。
人間同士のコミュニケーションは大きく以下の二つの種類に分けることができる。
①バーバルコミュニケーション
②ノンバーバルコミュニケーション
バーバルコミュニケーションとは、音声の「ことば」によるものである。ノンバーバルコミュニケーションは、「ことば」によらない意識的あるいは無意識的なメッセージのやりとりのことをいう。
人間が相手に意思や考えを伝える場合、言葉(バーバル)と同時にジェスチャや顔の表情などのノンバーバル言語を利用して表現しようとする。対面コミュニケーションで、私たちは音声以外に「ことば」でない言語を用いて絶えずメッセージを発信している。これは、コミュニケーションの種類にそれぞれ利点があり、人はそれをうまくとりいれて、豊かなコミュニケーションをとろうとするからであろう。
私たちは、ノンバーバルコミュニケーションの特長の一つである身振り手振りを用いて「ことば」に相当する意味を伝達する「手話」を詳しく調べることで、空間を利用して表現するコミュニケーションのやりとりをコミュニケーションに活用する研究を行った。
1.2 研究目的
本研究では、コミュニケーションの豊かさとはどういうものかを空間を利用し、手や身体全体の動きで表現する手話を用いて研究する。
そのために、①手話にはどういった特長があるか②手話はどのような利点があるかの2つの面を明らかにし、音声の「ことば」では難しいと考えられるコミュニケーションを空間表現で補うことを考える。
第2章 様々なコミュニケーション
2.1 人のコミュニケーションのやりとり
人間は、普段の生活の中で様々なコミュニケーションのやりとりを行っているが、コミュニケーションのやりとりの特長や、それぞれのコミュニケーションのやりとりにはどういった利点があるのかということはあまり考えない。ここでは、いくつかコミュニケーションのやりとりの例を挙げ、どういった特長があるのかを比較した。表1に人のコミュニケーションのやりとりを示す。
| 視覚言語 | 音声言語 | ||||||
| FAX | 手 話 | 手 紙 | テレビ | ラジオ | 電 話 | ||
| 言葉が目に見える | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | |
| 言葉を聞くことができる | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 離れた場所でコミュニケーション可能 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 労力をあまり使わない | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 複数のものを同時に表現可能 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 再生が可能 | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 感情のニュアンスが伝わる | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
この対応表から、人はそれぞれのコミュニケーションのやりとりの特長を生かして、様々なコミュニケーションに活用していることが分かる。音声の(ことば)の方が相手に分かりやすく伝わるもの、空間を利用して身振りや手振りの方が相手に分かりやすく伝わるものがある。日頃、自分達がどのようにコミュニケーションのやりとりをしているのかということをあまり考えることはないが、多くのやり方で人とコミュニケーションを行っている。
2.2 バーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーション
人間は、生活の中で音声言語や筆談、身振りや手振りなど実に様々なコミュニケーションを常に行っているが、それは大きく2つに分けることができる。バーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーションである。前者は「ことば」によるもの、後者は「ことば」によらないもの、つまり身体によるメッセージ表現に限られる。
例えば、映画館の中で近くの席にいた知人と顔が合ったとき、「こんにちは」と声で挨拶をするのは、バーバルコミュニケーションである。逆に会釈だけで済ませたり、手を振るなどして相手に親しみを伝えるなど「ことば」によらないメッセージ伝達がノンバーバルコミュニケーションである[2]。
2.3 空間を使う手話のバーバルな要素とノンバーバルな要素
手話は空間を利用して身振りや手振り、顔の表情などで自分の意思や考えを相手に伝える。空間を利用した身振りや手振り、顔の表情は、どれもノンバーバルコミュニケーションに当てはまる。しかし、手話は空間を利用した身振りや手振り、顔の表情を利用した「ことば」である。したがって、手話で利用する身振り手振りなどは、ノンバーバルな要素を含んでいると言えるが、ノンバーバルコミュニケーションとは言えない。空間を利用した身振り手振り、顔の表情自体が「ことば」なのである。つまり、手話の主体はバーバルコミュニケーションと言える[1]。
第3章 手話の概要
3.1 手話の歴史[1]
手話も言語なので、集団のない所には生まれてこない。このことから、手話は、ろうあ者集団が形成されるようになってつくられてきた。ろうあ者の集団が形成されるようになったのは、ろう教育が開始された明治11年頃からだと考えて良い。
手話は、教育の中で体系的に習ったわけでなく、またテレビやラジオ等で身につけていったわけでもない.ろうあ者集団の発展と共に発展してきた。また、手話は今も発展し続けていることばだと言える。
3.2 手話とは
手話とは、身振りや顔の表情など身体全体を使って意思や考えを相手に伝えるコミュニケーション手段である。また、手話は「聴覚言語」といった音声言語と違い、空間を活用して手の動きや身体全体の動きで表現する「視覚言語」である[3]。つまり、見ることばといえる。肩幅の広さで胸の位置で表現するのが手話の基本の表現である。また、手話の表現形式は単語の集まりである。単語と単語をつなげる助詞や格変化等を用いない。
【例】 音声の日本語 : 「私は花が好きです。」
手話 : (私)+ (花)+(好き)
このことから、音声言語と手話は表現の方法が異なるということが分かる。
3.3 手話表現の規則
手話表現では、①手の位置,②手の形,③手の動きが重要な役割を果たしている。以下に実際の手話表現の例を挙げる。




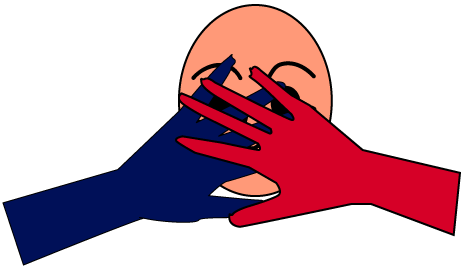

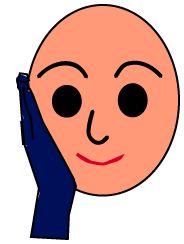




「肉じゃが作れるんですか、すごいですね。」




「最近、料理作りに凝っているんですよ。」




「今度は、何を作る予定ですか。」

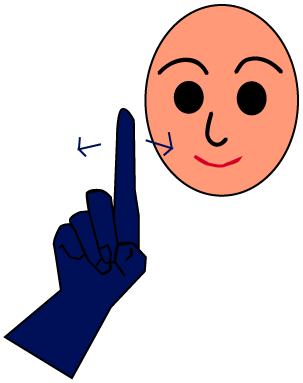


第4章 手話の解析
4.1 手話の手の動き、位置、角度の解析
(1)目 的
写真と絵を使うことで、平面的な2次元で手がどの位置でどのように動き、指の角度はどうなっているのかを解析する。
(2)方 法
①デジタルカメラで手話の手の動きを撮る。
②撮った写真をイラストレータで上からなぞり、絵にする(図7~25参照)。
③写真と絵を見ながら、手の形を解析する。
(3)結 果
静止しているため、手がどの位置でどのように動いているのか、指の形がどうなっているのか分かる。しかし、一方向からの絵であるため、立体的に見えないことや、手が動く速さが分からないなど、より細かいことに表現限界があるという問題が挙げられる。
4.2 3次元空間での手話の手の動きの解析
(1)目 的
2次元での解析に対し、3次元空間での手の動きを解析する。
(2)方 法
①イラストレーターで描いた4.1の絵を見ながらコンピュータに電子グローブを使って作成した会話文の単語と文の手の動きを入れていく。
②手の動きの変化をエクセルでグラフに表す。
③コンピュータに手の動きを学習させる。
(3)結 果
磁気センサと電子グローブを使うことにより、手の動きや位置、指の角度を立体的にとらえることができた。また、エクセルでコンピュータが読みとる手の動きや位置、指の角度を示したデータから、手がどのように変化するのか細かい部分まで明らかになった。
第5章 コミュニケーションに対する意識調査
5.1 目 的
人は職業やその人の個性などでコミュニケーションの取り方や意識が微妙に違うのではないかと考える。そこで、それぞれの立場の人(一般の人、マスメディアの仕事に携わっている人、手話でコミュニケーションをとっている人)に人とコミュニケーションをとるうえで、心がけていることはどんなことかをアンケートで明らかにする。一般の人には、日頃コミュニケーションをとる時、どのようなことを大切にしているのかを聞く。マスメディアの仕事に携わっている人には、仕事柄人とのコミュニケーションをとるうえでの心がけを聞く。その中でも、主に顔の表情の活用についてを聞く。手話でコミュニケーションをとっている人には、音声による「ことば」ではないため、どういうことに気をつけて人とコミュニケーションをとっているのかを聞く。
5.2 方 法
①それぞれのアンケートを作成する(付録参照)。
(一般97人、マスメディア10人、手話10人)
②アンケートを郵送したり、直接持って行く。
③アンケートの集計をエクセルでおこなう(付録参照)。
④明らかになったことをまとめる。
5.3 結果
(1)一般の人
①「5.人とのコミュニケーションを生活の中でどの程度重要だと思いますか」という質問に対し、「大変重要だ」「まあまあ重要だ」の2通りの意見に分かれ、重要ではないというような否定的に答えた人はいなかった。
②「6.人とコミュニケーションをとるときに大事にしていることは何ですか」という質問に対しては、「人とのコミュニケーションを和やかにするため、笑顔で話すようにしている」「相手の目を見て話すようにしている」「相手の顔の表情を見て話すようにしている」「言葉だけで説明できないことを身振りで表現している」など顔の表情など、ノンバーバルな要素を大事にしてコミュニケーションをとっていることが明らかになった(図26
参照)。


このようなアンケート結果から、一般の人は話す相手のことを考え、その場の雰囲気を和やかにしようと意識している人が多いことが分かった。また、人と話すときに、顔の表情を豊かにしたり、無意識のうちに身振り手振りを使って表現するという人も少人数見られた。全体的に一般の人たちのコミュニケーションでは、顔の表情や身振り手振りを使う等して、どうすれば相手に自分の言いたい事が伝わるのか意識しているというよりも、話す相手のことやその場の雰囲気を考えてコミュニケーションをとっているように感じられた。
(2)マスメディアの仕事に携わっている人
①「5.人とのコミュニケーションを生活の中でどの程度重要だと思いますか」という質問に対し、「大変重要」「わからない」の2つの意見に分かれた。「分からない」という答えは、アナウンサーやキャスターは、一対不特定多数であるため、コミュニケーションが成り立たないという考えからきているのではないかと思われる。
②「6.顔の表情をどのように活用しようと心がけていますか」という質問に対し選択肢で「周りの雰囲気を和やかにするためいつも笑顔で話す」「カメラのレンズを見て話すようにしている」と答えた人が多く、圧倒的に多かったのが「その他」であった。「その他」の意見で多かったのが「作った表情はしない」という答えであった(図28参照)。

③「7.手話を知っているか」という質問に対しては、「まあまあ知っている」「全然知らない」の2つの意見に分かれた。
④「8.人と話をする中で、身振り手振りを活用していますか」という質問に対して「ぜんぜん活用しない」と答えた人はいなかった。しかし、「あまり活用しない」「よく活用する」「わからない」と答えた人が同じくらいの数だった。
⑤「9.カメラを通して人に話をするとき、特に気をつけていることは何ですか」という質問を記述式でそれぞれの人に書いていただいた。そして、目立った答えが、「自然体でいること」であった。カメラの前でその場の状況などを伝えるためには、自然でいることで親近感がわく。逆に不自然な笑顔を作ることは、見る側も不自然に感じるため、マスメディアならではの答えではないかと感じた。
マスメディアの人達は、カメラの向こう側にいる不特定多数の人たちに相手が見えない状況で話をする。アンケートの回答の中で一番目立ったのが、「自然体でいること」という意見だった。不自然な表情・話し方にならないよう、いかに不特定多数の人に自然に話ができるかが大切なのではないだろうか。
また、アンケートの中で、不必要な身振り手振りはかえってわかりにくい表現になるという意見があり、身振り手振りは音声での表現をより分かりやすくするためのものだとしか考えていなかった私達にとって、とても参考になった。
また、アンケート自体に、「アンケートの選択肢が自分の考えていることと微妙に違うため、選びにくい」という言葉に関する指摘があった。このため、アンケートの内容、日本語をもう少し考え、工夫して分かりやすいものにする必要があった。
(3)手話でコミュニケーションをとっている人
①「5.人とのコミュニケーションを生活の中でどの程度重要だと思いますか」という質問に対し、すべての人が「大変重要である」と答えた。
②「6.手話でコミュニケーションをとっているとき、どういうことを心がけていますか」という質問に対しては、「手の動きだけでは説明できないことを顔の表情を使って相手に分かりやすく説明しようと心がけている」「手話は音声に比べて単語数が少ないため、その分顔の表情によって表現を補っていこうと心がけている」「相手の顔の表情をよく見て話そうと心がけている」という答えが多かった。音声による「ことば」ではないため、その分相手に的確に分かりやすく誤解のないように説明しようと顔の表情を使って、表現しようとするのではないだろうか(図
29参照)。



第7章 結 論
空間を活用して表現する手話を用いて調べることで、コミュニケーションとは何か、コミュニケーションの豊かさとはどういうものなのかを研究してきた。人と人とのコミュニケーションの中で、身振り・手振りや顔の表情の活用などコミュニケーションのとり方について新たな発見があり、さらに人とのコミュニケーションについて一人一人心がけていることが様々なことが分かり、コミュニケーションの奥の深さを感じた。
今回の研究で、空間を利用した身振り・手振りや顔の表情等は、コミュニケーションをとる上で有効な表現であることが分かった。身振り・手振り等は、口から発する音声言語での表現ではなく、身体全体を使った表現である。人の感情や相手に伝えたいと思う意思や考えなどは、身体全体、自分の全てで表現し、相手に伝えようとしなければ、人とのコミュニケーションは難しいのではないか。
情報化社会の中で、自分の意思や意見をしっかりともち、それを人に伝えることのできる力が必要である。これからは、自分の意思や意見をどのように表現すれば、相手に伝わるかという事も考えていかなければならない。
謝 辞
本研究にあたり、ご援助下さった手話講習会の小池スエ子先生、大分大学工学部情報システム学科の宇津宮教授、西野先生、アンケートにご協力下さった皆様に深く感謝致します。
参考文献
[1]大分県聴覚障害者協会:“手話学習・ボランティア活動の手引き”(1997).
[2]黒川隆夫:“ノンバーバルインタフェース”(1994).
[3]財団法人「全日本ろうあ連盟出版局」:新中級“手話教室”(1991).
[4]財団法人「全日本ろうあ連盟出版局」:“わたしたちの手話”(1969).
|
|
|||
 
両手の位置 |
近い 頃 料理 凝る |
両手位置の変化 |
近い 頃 料理 凝る |
|
|
|||
 
両手の方向 |
近い 頃 料理 凝る | 両手方向の変化 | 近い 頃 料理 凝る |
|
|
|
|
|||
 
両手の形 |
近い 頃 料理 凝る | 両手の形の変化分 | 近い 頃 料理 凝る |
|
|
|
||
セグメンテイション(語の区切り)
手の動作により言葉を伝える場合、音声並びに文字と同じように、単語の区切りが重要な処理になる。本研究では、電子グローブ及び磁気センサの出力の時系列を解析した。手の位置情報と方向は、極めて関係が強く、それらの変化値により大まかなセグメンテイションが可能なことが分かった。しかしながら、手の形の変化については、腕が静止している時に変化する場合、それが意味を持つ変化なのか、それとも、ある単語からある単語への移動なのかの見極めは、内容の情報なしには困難である。セグメンテイションは、意味情報(ニューラルネットワークなどによる学習)と個々の出力値による解析を総合的に行う必要があると考えられる。
解析例
本研究では、ビデオ、図式化、電子グローブのデータ値を解析することで、5つの手話会話から、手の動作単語のセグメンテイションに対する考察を行った。音声のセグメンテイションは、基準として、無音部分があり、音素の切り出しは、比較的容易であり、音声認識技術は限られた分野では、実用化の時期に来ている。手書き文字などの文字認識の分野は、画像処理、人工知能分野で研究が続けられている。音声、文字の認識とは違って、手の動作の認識は、基本動作の切り出しに、動作と動作の間の移行動作、無意識な動作などのノイズが加わり、セグメンテイション解決には、解決すべき多くの問題がある。今後は、基本動作知識、話者のコンテキスト(文脈)双方から、セグメンテイションを研究していくことが望まれる。
5.4コミュニケーションに対する意識調査
(1)一般の人へのアンケート(質問票)
1.性別(男、女)
2.年齢(10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代
3.職業(学生、その他)
4,地域(大分市、別府市、その他)
5.あなたは人とのコミュニケーションを生活の中でどの程度重要だと思っていますか。
ア.大変重要だ イ.まあまあ重要だ ウ.あまり重要ではない エ.全然重要ではない
6.あなたは人とコミュニケーションをとっている時、どういうことを最も大事にしていますか。
ア.人とのコミュニケーションを和やかにするため、笑顔で話す。
イ.相手の目を見て話すようにしている
ウ.相手の顔の表情を見て話すようにしている
エ.口をはっきり開けて話すようにしている
オ.言葉だけでは説明できないことを身振りで表現している
カ.内面的な感情を出すようにしている
キ.内面的な感情を出さないようにしている
ク.自分の意志や考えを相手により伝えるために、顔の表情を豊かにして日頃話すようにしている
ケ.スキンシップを多くとるようにしている
コ.特に気をつけていない
7.手話について知っていますか。
ア.手話ができる イ.手話が少しできる ウ.まあまあ知っている エ.全然知らない
8.人とコミュニケーションをとるとき身振り手振りを活用していますか。
ア.よく活用する イ.あまり活用していない ウ.全然活用しない エ.わからない
9.情報のやりとりにはどういう道具を使っていますか。よく使っているもの3つを選んで下さい。
ア.テレビ イ.新聞 ウ.雑誌 エ.電話 オ.手紙 カ.人との会話 キ.その他
10.コミュニケーションで特に気をつけていることを書いて下さい。
(例)笑顔で話す
( )
(2)マスメディアの人へのアンケート(質問票)
1~5の質問事項は、全て共通。
6.顔の表情をどのように活用しようと心がけていますか。
(一番心がけているものを3つ選んでください。)
ア.人とのコミュニケーションを和やかにするため、いつも笑顔で話すようにしている
イ.カメラのレンズを見て話すようにしている
ウ.口をはっきりと開ける
エ.内面的な感情を出すようにしている
オ.内面的な感情を出さないようにしている
カ.考えや意志が伝わるように顔の表情を豊かにする
キ.音声で説明できないことを身振りで表現しようとする
ク.特に気をつけていない
ケ.その他
7.手話について知っていますか。
ア.手話ができる イ.手話が少しできる ウ.まあまあ知っている エ.全然知らない
8.人とコミュニケーションをとるとき、身振り手振りを活用してますか。
ア.よく活用する イ.あまり活用しない ウ.全然活用しない エ.わからない
9.コミュニケーションで特に気をつけていることを書いて下さい。
( )
(3)手話でコミュニケーションをおこなっている人へのアンケート(質問票)
1~5の質問事項は全て共通。
6.手話でコミュニケーションをとっている時、どういうことを最も心がけていますか。
ア.人とのコミュニケーションを和やかにするため、笑顔で話すようにしている
イ.相手の目をよく見て話そうと心がけている
ウ.相手の顔の表情をよく見て話そうと心がけている
エ.相手の手の動きをよく見て話そうと心がけている
オ.口の動きをよく見て話そうと心がけている
カ.手の動きだけでは十分に説明できないこと(例えば、人の感情等)を顔の表情を使って相手に分かりやすく説明しようと心がけている
キ.手話は音声に比べ、単語数が少ないので、その分顔の表情によって表現を補っていこうと心がけている
ク.相手から見て分かりやすい、きれいな手の動きで話そうと心がけている
ケ.その他
7.手話によるコミュニケーションの利点にはどんなものがあると思いますか。
ア.騒音の激しい場所でも会話できる
イ.音声による「ことば」よりも表現しやすいものが多い
ウ.手の動き・顔の表情で感情を伝えやすい
エ.顔の表情が豊かになる
オ.あまり利点はない
カ.その他
8.音声言語によるコミュニケーションの利点にはどんなものがあると思いますか。
ア.自分の意思や考えを表現しやすい
イ.手話による「ことば」よりも表現しやすいものが多い
ウ.顔が見えなくても会話が成り立つ
エ.声のトーンで感情が分かる
オ.あまり利点はない
9.手話によるコミュニケーションで特に気をつけていることを書いて下さい。
( )
5.5 集計結果
(1)アンケートの集計結果






1.はじめに
コミュニケーションとは、「ことば」の音声表現、顔の表情、身振り手振りなどで相手に意思や考えを伝えるやりとりのことである。人間同士のコミュニケーションはバーバルコミュニケーション(「ことば」による)、ノンバーバルコミュニケーション(「ことば」によらない)の二種類に分けることができる。人間が相手に意思や考えを伝える場合、言葉と同時にジェスチャや顔の表情などのノンバーバル言語を利用する。人は言葉以外のやりとりをうまくとりいれて、豊かなコミュニケーションをとろうとする。私たちは、ノンバーバルコミュニケーションの特長の一つである身振り手振りを用いて「ことば」に相当する意味を伝達する手話を詳しく調べることで、空間を利用して表現するコミュニケーションのやりとりを豊かなコミュニケーションに活用する研究を行った。
2.研究目的
人は対話で使う「ことば」以外に筆談、身振りや手振りなど様々なコミュニケーションを行う[1.2](表1参照)。身振りや手振りを使ったコミュニケーションに手話が挙げられる。手話は空間を利用して身振りや手振り、顔の表情などで自分の意思や考えを相手に伝える。手話の空間を利用した身振り手振り、顔の表情などはノンバーバルな要素を含んでいるが、手話はバーバルコミュニケーションである。
私たちは、コミュニケーションの豊かさとはどういうものなのか空間を利用して表現する手話を用いて研究する。そのために、手話にはどういった特徴があるかを明らかにし、音声の「ことば」では難しいと感じるコミュニケーションを空間で表現することで補う。
3.手話コミュニケーション
手話は、「視覚言語」である。音声言語との最も大きな違いは、空間の利用にあり、肩幅の広さで胸の位置で表現するのが基本である。手話は、①位置,②形,③動きの3規則から成り立っており、どれも重要な役割を果たしている[1]。
手話は、単語の集まりで表現される。単語と単語をつなぐ助詞や格変化等を用いないため、たとえば日本語の「私は花が好きです」を手話で表現すると、「私 花 好き」という手の動きで表現される。このように音声言語と手話では表現の方法が異なる。
| 視 覚 言 | 語 音 声 言 語 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 言葉が目に見える |
|
|
|
|
|
|
| 言葉を聞くことができる |
|
|
|
|
|
|
| 離れた場所でコミュニケーション可能 |
|
|
|
|
|
|
| 労力をあまり使わない |
|
|
|
|
|
|
| 複数事物を同時に表現可能 |
|
|
|
|
|
|
| 再生が可能 |
|
|
|
|
|
|
| 感情のニュアンスが伝わる |
|
|
|
|
|
|




③ 結 果
磁気センサと電子グローブを使うことで、手の動きや位置、指の角度を立体的にとらえることができた。また、コンピュータが読みとる手の動きや位置、指の角度のデータから、手がどのように変化するかが明らかになった。
5.コミュニケーションに対する意識調査
① 目 的
それぞれの立場の人(一般の人、メディアの仕事に携わっている人、手話でコミュニケーションをとっている人)に、人とコミュニケーションをとるときに心がけていることはどんなことかを聞き、明らかにする。
② 内 容
1)一般の人へのアンケートは、日頃コミュニケーションをとるとき、どのようなことを大切にしているのかを聞く。
2)メディアの仕事に携わっている人には、仕事柄人とコミュニケーションをとるうえでの心がけを聞く。主に、顔の表情の活用についてを聞く。
3)手話でコミュニケーションをとっている人には、音声による「ことば」ではないためどういうことを一番心がけて人とコミュニケーションをとっているのかを聞く。
③ アンケート結果
アンケートの結果、大部分の人は共通してコミュニケーションは重要であると答えた。しかし、人とコミュニケーションをとる時、それぞれが心がけていることは違っていた。例えば、一般の人やマスメディアの人は、相手の気持ちやその場の雰囲気を考えて顔の表情を意識しているのに対し、手話でコミュニケーションをとっている人は相手に意思や考えを伝えるための手段として顔の表情を活用している。
空間を利用した身振り手振りは、それぞれが共通して、より相手に言いたいことや感情を伝えるために活用されていることが明らかになった。
6.課題と検討
コンピュータに読みとらせた手話の数が少なかったため、手の動きのデータが少ししか得られなかった。このため、手の動きの解析が限られてしまった。
コミュニケーションをどのように心がけているのかを調査するため、一般の人、マスメディアの人、手話でコミュニケーションをとっている人にそれぞれアンケートを行ったが、一般97人に対し、マスメディア、手話でコミュニケーションをとっている人、各10人と人数に極端に違いがあったため、正確な比較ができなかった。より多くの人達の考えを同数で聞く必要がある。
7.おわりに
手話の特徴を明らかにすることで、豊かなコミュニケーションとは何かを研究した。音声の「ことば」で、人の喜びや悲しみの程度、風の強さ、物の大きさ、物や人の位置関係などを、相手に伝えるのは難しい。手話は、手の動き・動きの速さ・手の位置・形等で話の内容、程度などが容易に理解できる。
空間を利用した身振り手振りを積極的に活用することで人との豊かなコミュニケーションを行うべきだと考える。
謝 辞
本研究にあたり、ご援助下さった手話講習会の小
池スエ子先生、大分大学工学部情報システム学科の宇津宮教授、西野先生、アンケートにご協力下さった皆様に深く感謝致します。
目次に戻る