
第1章 序 論
1.1 研究の背景
私たちは、家庭でも学校でも職場でも様々なメディアを使いながら日常生活を営んでいる。電話・手紙・本・新聞・テレビのようなパーソナルメディアやマスメディアから、ファクシミリ・ワープロ・パソコンなどの比較的新しいメディアに至るまで、多くのメディアを使うことによって、日常生活は非常に便利で能率的になった[1]。これまでの電話やファクシミリでは情報の受信・発信は何らかの関係のある当事者間で行われていた。パソコン通信では会員の間でのコミュニケーションに限られており、電話会社・パソコン通信会社の介在により初めて相互のコミュニケーションが可能であった。また、不特定多数のアクセスを可能とする伝達メディアは、新聞・出版・放送であり、個人・企業・団体などが情報を伝達するためには、新聞・出版・放送のような媒体を介して初めて伝達が可能であった。しかし、現在多く使われているインターネットでは伝統的な媒体に頼らなくても、個人・企業・団体が直接、情報の受信・発信を行うことができる。現在、全世界はネットワークで結ばれ、私たちは高度情報化社会の中で生活しているといえる[2]。情報化社会が発展し、私たちの生活は非常に便利で豊かなものとなった。しかし、多くの問題も起きている。「名誉毀損の問題」「プライバシー侵害の問題」「著作権侵害の問題」などである。これらの問題は、以前からあったものだが「情報処理技術の発達」で、より大きく、複雑になったのである。「情報処理技術」の基盤である「ディジタル複製」は、これらの問題に共通する原因と考える。また、誰でも簡単に「ディジタル複製」ができるようになったため、受け取る情報が誰のものなのか、どこからのものなのか、本当に真実の情報なのかがはっきりしなくなり、私たちはそれらを正しく判断することが難しくなっている。このことが、問題を複雑にしていると考える。情報が誰のものであるのかは「知的財産権」により明確にされる。「知的財産権」のなかで、情報化社会では「著作権」が中心となる。したがって、さまざまな問題の根本にあるものは「ディジタル複製」と財産権としての「著作権法」の関わり、そして「私たちの意識と知識」であると考える。
1.2 研究の目的
「情報処理技術」の中心といえるソフトウェア(プログラム)も「著作権法」で保護されている。そこでソフトウェアの著作権に注目して、「ディジタル複製」と財産権としての「著作権法」の関わりの実態を把握し、具体的にどのようなことが問題になっているのかを明らかにしていく。また、一般の著作権に対する意識と知識の実態をアンケートを通して明らかにする。そして、こうした問題を解決するためには、①技術はどう発展していけばよいのか、②新たにどのような制度が必要となってくるのかを考える。しかしながら、違法行為を行うことは技術的に容易で、しかも自分がしたということを自分が公表しない限り他人には知られにくいため法的な規制に限界がある。また、社会的に非難される情報の発信も法的な規制では限
界がある。そこで、③どのようなモラル が求められるのかも考える。このように、社会面・心理面・技術面
の3つの面から問題をとらえ、私たちが 今後どのように生活していけば、よりよ
い情報化社会をつくっていけるのかを考 察する。
第2章 ディジタル情報と情報
2.1 情報化社会
一般社会は、2つの世界が結合してい ると考えられる。
1つは、形のある「物」が生産・分配・消費される世界である。これには食べ物や衣服などが含まれる。この世界は人間の衣食住に関わっており、人間の生活の基礎となっている。そのため、一般社会においてもこの世界が基礎となっていると考えられる。もう1つは、形のない「情報」が生産・伝達・享受される世界である。ここで扱われる情報には、あらゆる情報が含まれる。この社会は、前者の「物の世界」を基盤として成り立っていると考えられる。このような社会の構造は、人間が共同生活をすれば必然的にできるものであり、人間が存在すれば、同時に存在するといえる。情報化社会とは、以上の2つの世界のうち、後者の「情報の世界」が技術的に発達し、社会や人間に必要とされ、重要視される社会をいう[3]。情報化社会の最大の特長は「情報が簡単に手に入る」ということである。これは、①時間の節約、②労力の節約、③お金の節約、④わずらわしさの減少という4つのことから示すことができる。「情報が簡単に手に入る」という特長の具体例として、インターネットについて述べる。インターネットの利用は、個人が家庭内にパソコン端末を備えることでインターネットへ直接アクセスし、情報の受信・発信を行うことが可能である。インターネットによるコミュニケーションの相手としては、あらゆる個人・企業・団体が考えられ、その範囲も国内だけにとどまらず世界中に広がっている。そのため、私たちは家にいながら様々な情報を簡単に手に入れることができるのである。以上の特徴から、情報化社会の進展によって、情報の制御権がこれまでのマスコミからわれわれの手に移ってきつつあるといえる。マスコミが持っていた巨大な力を覆してしまうほどの力を、私たち市民が持てる日も近いといえる。

2.2 情報処理技術
情報化が急速に発達した理由として「情報処理技術の発達」がある。この「情報処理技術」はコンピュータと電気通信を結合したものであり、この技術により情報の伝達・蓄積・処理を効率的に行うことができる[3]。このような伝達・蓄積・処理がスムーズに行われるために必要な技術に「ディジタル複製」がある。私たちがコンピュータを使って「ディジタル複製」を行う理由は、次のような利点があるからだと考える。
①情報を受信した人が直ちに応答したり他の人に送ったりできる。
②コンピュータ内のプログラム制御により記憶装置等に蓄積できる。
③蓄積された情報の一部を容易に変形処理できる。
④人間よりも高速・正確・大量に複製できる。
⑤これまでの複写・録画・録音と同程度に、あるいは、それ以上に品質の良い複製物を得ることができる。
このような理由から、「ディジタル複製」は「情報処理技術の発達」にとって非常に大切なものと考えられる。
第3章 ネットワーク上の著作権
3.1 著作権
著作者は「著作者人格権」と「著作権」の2つの権利を有する。「著作者人格権」は、著作者の人格的価値の保護を目的とする権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つから成る。「著作権」は、著作物の利用に関する財産的な利益を保護することを目的とした権利で、複製権・上演、演奏権・放送、有線送信権・口述権・展示権・上映権・頒布権・貸与権・翻訳、翻案権・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利から成る。「著作権」とは、著作者の持つ2つの権利のうちの1つである[4]。
著作物の規制についての基本法は著作権法である。これは昭和45年5月6日に公布され、翌46年1月1日より施行された。日本における近代的な著作権制度は明治32年に、国際的著作権保護に関するベルヌ条約への加盟のため制定された。これを改正して、著作権の国際基準にひき直したのが現行著作権法である。45年改正著作権法は全7章124カ条より成っている。改正著作権法は、以下の6つの特徴を持つ。
①著作者人格権の保護の強化
公表権・氏名表示権・同一性保持権の3種の権利を著作者人格権という名称を付して正面から認めた。
②保護期間の延長
死後30年としていた保護期間を、ベルヌ条約ブラッセル規定と同じ死後50年に延長し、世界の大勢に合致させた。
③映画著作権の帰属に関する規定を新設
いわば総合芸術ともいえる映画について、映画の著作者となりうる者から小説・脚本音楽その他の著作物の著作者を除外し、制作、監督、演出、撮影、美術のいずれかを担当する者を著作者とする旨、新規定をおいた。
④翻訳権10年留保の撤廃
翻訳権の保護期間を10年としていたが国際的な実状にあわせるべくこの留保を撤廃した。経過規定の定めにより、現行法施行後に発行されたものについて、10年留保を撤廃したため昭和46年1月1日以降より、すべての翻訳物に保護期間50年が適用されることとなった。
⑤著作隣接権の創設
著作物たる詩・音楽・脚本等を利用する者ではあるが自らを著作者とすることに疑問のあった実演家、レコード制作者、放送事業者を著作隣接権者として、それぞれに著作権に準じた権利を与えることとした。
⑥自由利用、法定許諾、強制許諾についての変更
著作者の許諾を得ないで著作物を利用すると権利侵害になるというのが、著作権法の根幹をなす。著作権法は、特定の場合にのみ対価を支払わずに自由に利用することを認めているが、そのほかに補償金を支払って自由にできる場合(法定許諾)と、許諾を求めたが対価について合意に至らないときに文化庁長官に裁定を求めてその対価を決定してもらい、その対価を支払って利用できる場合(強制許諾)を定めた[5]。情報化社会では、文字・音声・画像・データを複合的に利用するが、このような文字・音声・画像・データなどを保護し、権利関係を規制する法律は、著作権法が中心になる。技術的な意味で特許その他の知的財産権も絡むが、対象となる情報・データ・表現などを保護するという意味では、知的財産権のなかの著作権が中心的な権利になる[6]。
表1
著作者の持つ権利
| 著作者の持つ権利 | |
| 著作者人格権 | 著作権 |
| ・公表権
・氏名表示権 ・同一保持権 |
・複製権
・上演、演奏権 ・放送、有線送信権 ・口述権 ・展示権 ・上映権 ・頒布権 ・翻訳、翻案権 ・二次的著作物の利用に関する権利 |
| 知的財産法 | |
| 権利付与構成を取るもの | 行為規制の構成を取るもの |
| ・特許法(発明)
・実用新案法(考案) ・意匠法(意匠) ・商標法(商標) ・半導体集積回路の回路配置に関する法律 (半導体のレイアウト) ・種苗法(植物の新製品) ・著作権法(著作物) |
・不正競争防止法
(標識、営業秘密、商品形態) |

著作権法ではソフトウェアは「電子計算機を機能させて1つの結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう」と、定義されている。
①「電子計算機」とはコンピュータのことをいう。コンピュータは演算・制御・記憶・入力・出力の5種類の機能を有するとされているが、ここでいう電子計算機は、入力・出力の機能がなくても演算・制御・記憶の機能を備え ていれば足りると考えられる。
②「機能させる」とは、コンピュータを用法に従って稼働させることを意味する。
③「1つの結果を得ることができ る」とは、なんらかの意味をもった1つの仕事をすることができるということである。ここでは、1つの財産的価値を持つに至るまでまとまった結果であることが要求される。
④「これに対する指令」とは、コンピュータに対する命令をいう。
⑤「指令を組み合わせたもの」とは、2個以上の指令が存在し、その組み合わせ方に意味があることをいう。命令の組み合わせがプログラムの最も本質的なものであり、「1つの結果を得ることができるように」組み合わされていることが必要である。
⑥「表現」とは、ソフトウェアが著作物である以上当然要求されるものであるが、ソフトウェアの性質上、他の著作物とはかなり違ったものも含まれる。紙に書かれたソース・プログラムのように、比較的従来の「表現」の概 念に近いものだけでなく、磁気ディスク、磁気テープ等に収納したり、マイクロチップや機械装置に記憶するも のも「表現」であるとしないと、法の正しい適用が得られない。もっとも、「表現」というからには、なんらかの機 器の助けを借りてでも、人間の五感によって内容を知覚しうるものであることが必要である[7]。
3.3 著作権法の問題
情報化社会では、情報技術(コンピュータ技術+通信技術)の進歩と比べて法律的な対応、制度化への努力はあまりにも時間がかかりすぎるため、従来、社会問題に対して有効であった法律は、情報技術に対して有効性を持たないといえる[8]。このことから、情報化社会における法律のあり方自体が問題になる。
情報化社会では、「著作権法」が実状と合わない部分が生じている。情報化社会での著作権処理の特殊な問題としては、以下の4点である[6]
①利用方法が伝統的利用方法と異なるため、伝達の主体が不明確になること。
②双方向的な利用により、改変や二次的著作物の利用の問題が生じること。
③情報の複合利用について、特に同一性保持権という人格権を侵害しないか、翻訳権の侵害にどう対処するかということ。
④ディジタル化によって同一物ができることと、質的に劣化したものができることで人格権侵害の問題が生じること。
これらの問題は、ディジタル化された情報が「著作権法」で保護されていることから生じた問題と言える。したがって、「著作権法」の見直しが早急に必要であると考える。また以下の4点が、これらの問題を複雑にしていると考えられる。
①もともと著作権は権利関係が複雑である。
②一般に著作権に対する意識が低い。
③著作者の権利を侵害する複製が技術的に容易である。
④不正行為を行ったことは自分が公表しない限り他人には知られない。
第4章 意識調査
4.1 調査の背景・目的
「名誉毀損の問題」「プライバシー侵害の問題」「著作権侵害の問題」などさまざまな問題を複雑にしている原因として、「私たちの意識と知識」が考えられる。そこで、実際にどの程度著作権を意識しているのか、著作権に関する知識はどの程度かを明らかにするため、アンケートによる調査を行う。また、一般の方と日常生活でコンピュータをよく利用する方の意識の格差を明らかにする。
4.2 調査方法
(1)調査期間:平成9年12月~12月末
(2)調査対象:①一般の方43名 ②別府大学短期大学部学生、大分県立芸術文化短期大学学生149名③日常生活でコンピュータをよく使用する方75名
(3)調査方法:紙面、電子メイルによる調査(アンケート)
(4)調査内容:①複製がどの程度行われているか ②著作権の理解度テスト③著作権に対する意識
4.3 調査結果
(1)学生(149名)・一般(43名)・日常生活でコンピュータをよく使用する方(75名)に共通する質問の結果を以下に挙げる。
Q性別

一般は男性44.2%、女性55.8%とほぼ半分である。学生は大分県立芸術文化短期大学の学生の学生を対象としたため男性9.5%、女性90.5%と女性が圧倒的に多い。日常生活でコンピュータを使う人では男性90.6%、女性9.4%と男性が圧倒的に多い。 男性が多い理由は①扱われる情報が、男性の求める情報であることが多い、②女性の機械に対する苦手意識が強い、③コンピュータを使えるようにする準備が難しく、女性が敬遠しがち、④コンピュータを扱う機会が男性の方が多い、などが考えられる。
Qあなたは出版物(本・雑誌等)をコピーするようなことがありますか。

Q次の項目のうち著作権上、合法だと思うものには○、違法だと思うものには×、どちらとも言えないと思うものには△を記入してください。
①レンタルショップで借りたビデオをダビングする。
②教師が授業のために本の一部をコピーし、資料にして生徒に配る。
③自分のホームページに曲を流すのに自分の好きな歌手のCDを使う。
④会社内で仕事のために市販のソフトをコピーする。
⑤自分で買った市販のソフトをバックアップ用コピー以外にコピーする。
⑥一つの市販のソフトを指定台数より多いコンピュータで使用する。
⑦自分で買った市販のソフトを友人のためにコピーする。
⑧自分で買った市販のソフトを独自に改造して、自分ひとりで使う。
⑨自分で買った市販のソフトを友人に譲り、自分はあらかじめコピーしてあっ
たものを使う。
⑩購入したソフトが違法に複製されたものとは知らずに使う。
|
|
|
|
|
|
①レンタルショップで借りたビデオをダビングする。 |
 |
 |
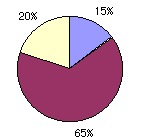 |
|
②教師が授業のために本の一部をコピーし資料にして生徒に配る。
|
 |
 |
 |
|
③自分のホームページに曲を流すのに自分の好きな歌手のCDを使う。
|
 |
 |
 |
|
④会社内で仕事のために市販のソフトをコピーする。
|
 |
 |
 |
|
⑤自分で買った市販のソフトをバックアップ用コピー以外にコピーする。
|
 |
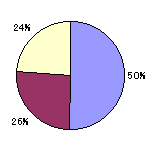 |
 |
|
⑥一つの市販のソフトを指定台数より多いコンピュータで使用する。 |
 |
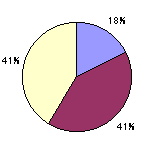 |
 |
|
⑦自分で買った市販のソフトを友人のためにコピーする。
|
 |
 |
 |
|
⑧自分で買った市販のソフトを独自に改造して自分一人で使う。
|
 |
 |
 |
|
⑨自分で買った市販のソフトを友人に譲り、自分はあらかじめコピーしてあったものを使う。
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
【意識調査採点基準】
①× レンタルショップで借りたビデオのダビングは法律で禁止されている。
②△ 許諾を得ない場合は、教育に必要と認められる限度を超えて利用することは
できない。教育に必要と認められる限度はごく小規模であり、一般的には違 法と考えて良い。
③× 許諾を得なければ、利用することはできない。
④△ 仕事のためであっても、原則として市販のソフトをコピーすることは違法と
される。
⑤× バックアップコピーは1度しかしてはいけない。
⑥× 指定された台数より多くコンピュータで使用してはいけない。
⑦× ソフトは私的使用の範囲内では複製を行ってもよいが、この場合は私的使用
の範囲をこえている。
⑧○ 市販のソフトを改造し、自分ひとりで使うのはよいが、それを他人に渡した
りすると違法になる。
⑨× 市販のソフトを譲り手元になくなった時点で、自分の所有権はなくなり、あ
らかじめコピーしてあったもの (バックアップ用コピー)は処分しなければ
ならない。
⑩○ 違法に複製されたソフトと知らずに使用していた場合は、違法にならない。



Q情報化によって著作権は侵害されやすくなると思いますか。

「思う」と答えた人は、一般88.6%、学生74.8%、日常生活でコンピュータをよく使用する人72.2%である。全体的に「思う」と答えた人が80~90%程度で圧倒的に多い。日常生活でコンピュータをよく使用する人に「思わない」と答えた人が15.2%と一般0%、学生2.2%より多かったのは、一般・学生よりも技術的な知識があり、解決策の見通しがあるからではないかと考える。
(2)一般の方(43名)・学生(149名)のアンケート結果を以下に挙げる。一般・学生・日常生活でコンピュータをよく使用する方に共通する質問については、(1)の結果を参照する。
Q1.性別(図3参照)
Q2.年齢

Q3.あなたはインターネットを使ったことがありますか。

一般は、「よく使う」と答えた人が4.7%「ときどき使う」と答えた人が14.0%である。学生は「よく使う」と答えた人が3.4%「ときどき使う」と答えた人が17.7%であ る。一般・学生ともに「よく使う」「とき どき使う」と答えた人が20%程度である。 一般で「あまり使わない」と答えた人は16.3%、「全く使わない」と答えた人は65.1%である。学生で「あまり使わない」と答えた人は34.7%、「全く使わない」と答えた人は44.2%である。一般・学生ともに 「あまり使わない」「全く使わない」と答 えた人が80%程度である。現在インターネ ットが注目され、人気が高まっているため 使用率はもっと高いと予想したが、予想に反した結果となった。全体的に、インター ネットの使用率は低いといえる。
Q4.あなたは電子メイルを使ったことがありますか。

一般で「よく使う」「ときどき使う」と答えた人は9.3%である。学生で「よく使う」「ときどき使う」と答えた人は11.0%である。一般・学生ともに10%程度である。 一般で「あまり使わない」と答えた人は18.6%、「全く使わない」と答えた人は72.1%である。学生で「あまり使わない」と答えた人は37.0%、「全く使わない」と答えた人は52.1%である。一般・学生ともに 「あまり使わない」「全く使わない」と答 えた人が90%程度であり、インターネット の使用率よりもさらに低いといえる。
Q5.あなたは出版物(本・雑誌等)をコピーするようなことがありますか(図4参照)。
Q6.日頃、著作権を意識してコンピュータを使いますか(図8参照)。
Q7.次の項目のうち著作権上、合法だと思うものには○、違法だと思うものには×、どちらともいえないと思うものには△を記入して下さい(図5.6.7参照)。
Q8.あなたはあなたの作ったものが無断で使われたことがありますか。

「ある」と答えた人は、一般3.1%、学生0%で非常に少ない。「ない」と答えた 人が、一般81.3%、学生79.2%で、一般・学生ともに80%程度で圧倒的に多い。「わからない」と答えた人は、一般15.6%、学生20.8%であった。
Q9.情報化によって著作権は侵害されやすくなると思いますか(図9参照)。
(3)日常生活でコンピュータをよく使用する方(75名)のアンケート結果を以下に挙げる。一般・学生・日常生活でコンピュータをよく使用する方に共通する質問については、(1)の結果を参照する。
Q1.性別(図3参照)。
Q2.年齢

10代が0%、20代が14.1%、30代が46.9%、40代が23.4%、50代が14.1%で、60代・70代は非常に少ない。
Q3.あなたはインターネットをどれくらい使用しますか。

Q4.どのようなものをダウンロードしますか。具体的に教えて下さい。


Q6.友人から借りた市販のソフトを自分のコンピュータにインストールすることがありますか。

「よくする」「ときどきする」と答えた人がが22.4%、「あまりしない」と答 えた人が26.3%、「全くしない」と答え た人が51.3%である。「あまりしない」「全くしない」と答えた人が圧倒的に多 く、「よくする」「ときどきする」と答えたは少ない。この結果から、この違 法行為は行われているといえるが、違法行為が一般的とはいえない。「よくす る」「ときどきする」と答えた人は22.4 %と比較的少なかったが、借りたソフト を自分のコンピュータにインストールす ることが違法であると知っている人が、 実際にそのような行為を行っていても 「行っていない」と答えた可能性がない ともいえない。
Q7.あなたは自分のホームページを持っていますか。

「持っている」と答えた人が45.7%「持っていない」と答えた人が54.3%でホームページを持っている人と持っていない人はほぼ半分である。
Q8.ネットワーク上ではあなたの知らないところであなたのホームページの絵や文章が使われることが考えられます。あなたはホームページを持つうえでそのようなことが心配ですか。

「非常に心配している」と答えた人が2.7%、「少し心配している」と答えた人が24.3%、「あまり心配していない」と答えた人が62.2%、「全く心配していない」と答えた人が10.8%である。全体的に、深刻に心配はしていないといえる。アンケートの中で「いちいち許諾を求められるのが面 倒」という意見もあった。
Q9.他人のホームページにあったものを、無断で自分のホームページに使うことがありますか。
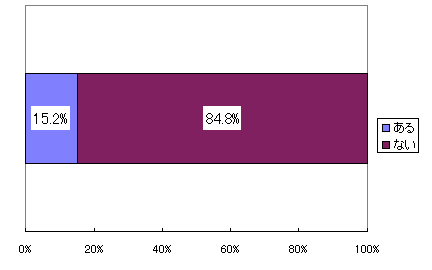
「ある」と答えた人が15.2%、「ない」と答えた人が84.8%で「ない」と答えた人が圧倒的に多い。しかし、この問題は問題文から違法行為だと感じられるため、このような行為を行っていても「ない」と答えた人がいる可能性がないともいえない。
Q10.あなたはあなたのつくったものを無断で使われたことがありますか。

「ある」と答えた人は5.9%と少なく、「ない」と答えた人は35.3%と比較的多い。「わからない」と答えた人が58.8%と非常に多く、無断で使われていること自体が本人にも分かりづらく、不明確であると言える。
Q11.あなたは出版物(本・雑誌等)をコピーするようなことがありますか(図4参照)。
Q12.日頃、著作権を意識してコンピュータを使いますか(図8参照)。
Q13.コンピュータを使えば誰もが簡単にコピーを行うことができます。そこで著作権を侵害するような行為は一般的に行われていると思いますか。

「思う」と答えた人が96.3%と圧倒的に多く、「思わない」「わからない」と答えた人は、ごくわずかである。著作者の権利を侵害するような行為が実際、一般的に行われているとはいえないが、ほとんどの人が「一般的に行われていると思う」と答えているため、このような行為が一般的に行われている可能性がある。
Q14.また、そのような行為は今後なくなると思いますか。

「思う」「わからない」と答えた人は10.1%とごくわずかで、「思わない」と答えた人は90%と、圧倒的に多い。
Q15.次の項目のうち著作権上、合法だと思うものには○、違法だと思うものには×、どちらともいえないと思うものには△を記入して下さい(図5.6.7参照)。
Q16.情報化によって著作権は侵害されすくなると思いますか(図9参照)。
このアンケート結果より、全体的に、著作権に対する意識と知識が低いことがわかった。特に学生の意識と知識が非常に低い。これから社会にでて、コンピュータを扱って行くであろう学生が、著作権に対する意識が低いというのは問題であると考える。また、現在は「著作者の権利を侵害するような行為はなくならない」と考える人が多いという結果がでたが、これから「なくなると思う」と考える人が多くなるように、ざまざまな面から社会全体が対応していかなければならないと考える。
第5章 考察(結果と検討)
5.1 技術面
(1)複製防止システム
許諾を得ずに複製されるのを防ぐための技術である。たとえば、複製しても使用できなくするための暗号化技術などがある。
(2)著作権管理・処理技術
利用を許諾するために必要な情報を標準形式で添付しそれを処理する技術である。たとえば、ソフトウェアの実行を含め、様々な利用形態に対応してきめ細かくお金をかける超流通技術などがある。今後、それらの技術の効率と適用範囲を評価し、積極的に導入を進めることが必要であると考える。また、これらの技術が適性に運用されることを支援するための制度と組織が必要となる可能性がある[3]。
5.2 社会面
(1)プロバイダの責任の明確化
現在のプロバイダの責任については、プロバイダ等電気通信事業者は通信役務を提供しているにすぎず、通信の内容に関与する立場にはないから、原則としては、犯罪または権利侵害の責任を負うことはないと考えられる。しかし、プロバイダが自らの情報発信に関して責任を持つのは当然であるといえる。プロバイダの責任を明確化することで、犯罪または権利侵害を情報発信の時点で、ある程度防ぐことができると考える[9①]。
(2)権利の集中管理体制の充実
著作物の権利や利用条件などの権利情報を提供する体制を整備することで、著作者を明らかにすることができる。文化庁では、このようなシステムの実現を目指し、平成7年度から調査研究を実施している。
(3)著作権法の見直し
ディジタル化された情報が円滑に権利処理されるようなルールやシステムを確立することが必要であると考える。①新しい権利の必要性、②人格権のあり方、③制限規定の見直しの必要性、④複製や受信の技術的制限の解除装置の規制の必要性、⑤情報をディジタル化した者や送信業者の保護の必要性、⑥映画に関する規定の見直しの必要性などを、今後検討することが必要である。
(4)情報の流通の促進
不正行為が行われる原因は、正しい方法で情報を得るよりも手間がかからないからだと考える。したがって、手間のかからないシステムを確立することが必要である。このシステムを確立するうえで必要な4つのことをあげる。
①技術開発に対する中立性、柔軟性
急速に進展する情報技術の開発の自由度を奪わず、技術開発を勧める側の予測可能性にも配慮したルールづくりの推進が必要である。
②販売手法の多様化に対する柔軟性
ディジタル・ネットワーク環境を通じて、物流の時代にはやりにくかった少量単位からのコンテンツの切り売りや使用法に応じたさまざまな価格設定、商品の組み合わせといった多様なサービスや販売手法の可能性が競争を活性化させるような市場作りの推進が必要である。
③コスト効率の良いシステム作り
金銭、時間、情報量などで総合的に評価した情報伝達コストの低減とそれによる流通の活性化を促すようなコスト効率よい取引管理システム作りが必要である。
④ユーザーの嗜好の変化に対する柔軟性
ユーザーの嗜好の変化に対応した商品や販売手法の開発に柔軟に対応できるルー
ル作りが必要である[9③]。
5.3 心理面
技術面・社会面で、どんなに厳密に著作権を保護しようとしてもやはりすべては補いきれず、それを補うのに心理面の意識が挙げられる。どうして規則があるのか、どうして規則を守らなければならないのかを理解し、法律でしてはいけないとされていることはしない、自分の権利を守るように人の権利も守るといったことを、当たり前のこととしてとらえることが必要である。
5.4 専門家の意見
専門家の意見として別府大学短期大学部森田均助教授と大分県立芸術文化短期大学松井修視助教授に意見を伺った。
森田先生は、「今までは法律がプロ対プロのやり取りのためにあったが、一人一人が情報発信者となった現在では、一般ユーザと法律を結びつける制度・機関が必要になる。」という意見であった。また本研究考察の技術面での「超流通技術」に関しては、個人向けではないので効果は期待し難いとの意見であった。
松井先生は、「情報の自由な流れを豊にすることを基盤にして、著作権を守る仕組みを考えていくのが良い」という意見で、本研究社会面で述べた「情報の流通の促進」が著作権を考える上での基盤になるという考えに賛同的であった。
第6章 結 論
私たちは、よりよい情報化社会をつくっていくためにどうすればいいのかを「ディジタル複製」と「著作権法」の関わりを通して、技術面・社会面・心理面の3つの面から追究してきた。その結果、技術面・社会面での対策はこれから当然必要となってくるが、心理面での対策が最も必要だと考える。人間は、どうしても自分の利益を優先してしまいがちであるが、自分の利益を守りたいのであれば、他人の利益も当然守らなければならない。このことは、今まで知らなかったからできなかったのではなく、わかっていながらできなかったことである。したがって、当然のことが当然のこととしてできる人間を育成するために、教育を見直していくべきだと考える。情報倫理を積極的に取り入れた授業を行うべきである。情報倫理とは「情報化社会においてわれわれが社会生活を営む上で、他人の権利との衝突を避けるべく、各個人が最低限守るべきルール」であり、情報を活用した
①プライバシー・知的財産権の侵害、
②情報システムの破壊、
③情報やその伝達媒体の不正利用、
④情報の不正な複製などの不正行為を抑止、防止、
などを行うことで情報社会の健全な発達を促進させることが目的である[8]。情報倫理の授業を取り入れたり、実際にコンピュータを使い経験したりして、幼いころから情報倫理を学ぶことが必要であると考える。そして、個人個人が情報の価値を判断できる力を養うことが必要である。社会が高度になっていくのならば、人間も高度になっていかなければならないと私たちは考える。
謝 辞
本研究にあたりご助言ご援助くださいました東京大学の浜田純一教授、別府大学短期大学部の森田均助教授、本学科の松井修視助教授、本学科非常勤講師の渡辺律子先生、本学科実習助手の中島順美先生、アンケートにご協力下さいました皆様に深く感謝いたします。